登山に挑戦したいけど、山で遭難などのトラブルに遭うのが心配、、、
そんな方への、山でよくある遭難と、対策について紹介します。
登山中の遭難で、多い原因は何?

警視庁の調べによると、2023年の登山遭難件数は、全国で3,126件発生しています。遭難者数は3,568人で、そのうち死者・行方不明者は335人、負傷者は1,400人、無事救助された人は1,833人でした。
シーズンでは夏山が最多です。
遭難の原因別にみると、道迷いが33%を占め、転滑落が20%、転倒16.9%、疲労8.6%、病気9.3%となっています。これは、無事救助された人も含む遭難者全体の原因別の割合です。
遭難し、亡くなった方のみの原因の内訳はデータ化されていないようですが、こんなサイトを見つけました。
直近のデータがありませんが、長野県の2017年の遭難者の死因としては、転滑落が最も多く、ついで、病気になっています。これは、2024年の今でもほとんど割合は変わらないと思われます。
遭難?事故手前・・わたしの体験談

遭難し、警察のお世話になるには至らなかったですが、私も山でのトラブルを経験したことがあります。4つ紹介します。
ソロ山行で道迷いした件
登山を始めて間もないころ、丹沢のマイナールートをソロで歩いた際に発生。事前に道を調べていたものの、事前情報となんとなく違うな・・と違和感を感じていたのに変な尾根に上がってしまい、その尾根が進むにつれてどんどん足元が悪くなっていったところで、「これは違う!」と道迷いしたことに気づきました。
でも、急峻で脆い尾根は、下るのも危険な状況。
たまたま、直前にガイド山行で丹沢エリアの破線ルートを案内してもらっており、その時にガイドさんから教わっていた「道迷いしたら下らずに上がること。そうすればいつか登山道に合流できるから。」という教えを信じて、恐怖心と一人戦いながら尾根を上がっていったところ、本当にガイドさんの言う通りに登山道に合流して、めちゃくちゃホッとしたのを覚えています。
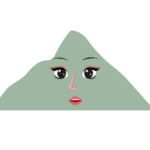
あの時ガイド山行に行かず、道迷い時のノウハウを知らずに尾根を下っていたら、登山歴1年で私の人生は終わっていたかもね・・・
テント内で倒れた件
1つは、自分自身のテント内での一酸化中毒。数名で同じテントに入っていたのに、なぜか一番テント入口に近い私だけが体調不良になりました(^^;)
お酒を飲みながら、換気口を開放したテント内で調理をしており、まだビール1杯目なのになぜかすごく酔いが回るなー・・と思っていたら、全身脱力して動けなくなり、その場に倒れました。
すぐに友人たちがテントの外に引っ張り出してくれて、新鮮な酸素を吸うことができたので、10分くらいして回復し事なきを得ましたが、あれがソロのテント泊だと思うと・・・・または全員がテント内で倒れてしまったら・・・
誰にも気づかれずに翌朝テントの中で冷たくなっていた、ということもあり得たかもしれません。
滑落した人が降ってきた件
私自身が遭難したわけではないですが、北アルプスの岩場が多い山岳地帯を歩いていた時に発生。
上から人が降ってきたことがあります。滑落者です。
その人は運よく(?)登山道上に落ちてきて、意識はもうろうでしたが呼吸もしており、周囲の登山者の中に看護師さんがいたので、安定した登山道上で適切な処置ができ、ヘリで救助されていきました。
これも、自分を含めた登山者に激突していたり、日没間近だったら・・・などと考えると、犠牲者が増えていたかもしれないし、当日の救助ができず滑落者の命が助からなかったかもしれません。
自分が滑落しなくても、滑落した人による二次被害まではそれまで考えたことがなかったので、そのようなリスクも胸にとどめておきたいと思いました。
仲間が足が攣って下山遅れした件
よく歩かれていて、小屋もいくつかある登山道にて発生。普段から足をつりやすい友人が、途中から足を攣り、薬を飲んでだましだまし歩いていたが、夕方になりいよいよ歩けなくなってしまいました。
来た道を戻り、あと標高で200mくらい登り返せば山頂の小屋なのに、介助歩行もできず、急登なので徒手搬送するにも時間がかかる。結局攣りが収まったタイミングを見ながらゆっくり小屋まで歩き、小屋に着いたのは15時半。
足を攣った本人とその付き添い1名は小屋泊することとしたものの、小屋がほぼ満員で断られたため、私を含めた他の3人は夕方から下山を開始(本当は一緒に下山するのがベストですが)。
下りは破線ルートであまり歩かれていない道だったため、不明瞭な箇所が多いうえに夜になってしまいライトをつけながら下山するも、ピンクテープのマーキングの間隔が広すぎて全然見つからなくなり・・・。あきらめて、ココでビバークか・・・というときに、奇跡的にピンクテープを再度見つけて、そこからは等間隔にマーキングがあったので、20時近くにやっと下山できました。地図とコンパスがあり、日帰りであってもガスとツェルトがあったためビバークも検討できたのが救いでした。
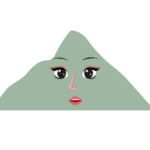
それにしても、緊急なんだから泊めてほしかった・・・
登山の遭難対策としてできることは?

登山で遭難するのを防ぐに様々な対策が必要です。
ここでは、遭難の原因別に対策を考えてみたいと思います。
基本的な対策
原因別対策の前に、登山に行くとなった場合に必要な基本的な遭難対策について説明します。
1 登山計画書を提出し、登山時には紙でも携行する
登山計画書を作成して、警察に提出しましょう。毎回やるの、面倒ですが必ずやってください。また、作成した計画書は提出用と、携行用と2枚持っておくこと。
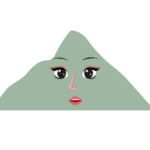
山岳遭難で110通報した場合に、同行者などの個人情報を聞かれるので、紙ですぐみられると便利だからです!
作成したものは、都道府県によって提出方法が異なりますが、メール送付、登山ポストへの投函、電子申請、郵送などがメインです。
様式と各都道府県警への送付方法はhttps://www.jma-sangaku.or.jp/sangaku/plan/に掲載されています。
また、「コンパス」という登山届を電子申請でできるサイトもあります。コンパスで山行届を提出すると、自治体や警察にも登山届が共有されます。昔は、コンパスと連携している自治体が長野や岐阜などの大きな山岳地帯を持つ地域に限られていましたが、今はほとんどの自治体が連携しています。compass
2 山岳捜索サービスを利用する
頻繁に登山する人は、「ココヘリ」に加入すると良いです。電波を飛ばす小さな発信機を登山に携行することで、遭難した際にも居場所を速やかに特定してくれるものです。発見率は96%とかなり高いです。
また、遭難時の捜索費用や、他人を怪我させてしまった時の個人賠償責任制度も付帯しています。
ただし、ココヘリも、専用サイトから登山届を出す必要がありますのでご注意を。
レンタルサービスは無いので、ごくたまに山に行く人にはお勧めしません・・・
3 家族や友人に行先を告げる
作成した登山届を友人や家族に共有しておきましょう。できれば複数へ共有したほうがいいし、可能ならば山のコトを知っている人に共有しておくと、有事の際に話が早いです。
4 時間に余裕を持った行動をする
私の体験のように、明るければなんてことない山道も、暗くなった途端に難易度が上がります。
計画を作る際には、普段自分が登山地図に載っているコースタイムの何割くらいの速さで歩いているかを確認し、目的地まで無理なく歩けるようにスタート時間を逆算しましょう。
5 衛星通信ができる機器を持つ
こう書いておいておきながら、私は持っておりません(笑)が、ほしいと思っているものの上位に入ります。
ガーミンの「inReach」は、衛星通信が可能な端末で、スマホの電波がない場所でも緊急連絡先との位置情報の共有や、メッセージ送信、SOSの要請などができる機能を持っています。うーん、ほしい・・・
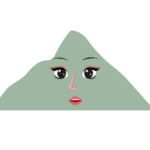
私も滑落者の対応で通報の手伝いをしたとき、電波が弱すぎな場所から電話を掛けましたが、電話が切れたり、切れてはいないが通話ができなかったりして、内容を伝えるのにかなり時間がかかりました。そうした時、衛星端末があればもっと迅速な通報ができたのでは?と思います。
6 複数人で行く
私的に、ベストなパーティーの人数は3人以上だと思っています。
例えば誰か1名が滑落や病気で動けなくなった時、大きくわけて処置と救助要請の2つの作業が必要となります。
2人以上いればそれらを分担して同時進行できますし、もしその場で電波がなくて通報できず、少し離れた電波の入るところまで行く必要があるときに、2人パーティーだとけが人(病人)を一人残していくことになり、離れているうちに容態変化などがあるかもしれないので心配ですよね。救助者が2人いれば、付き添い役で一人はけが人のそばに置いていくことができます。
そういう意味でも、パーティーは3人以上が良いかなと思います。
そうは行っても私も2人で行くことが多いんですがね・・・。
道迷いの対策
道迷いしないために必要なことを挙げてみます。
1 事前に地図をみてルートを確認する。
当たり前ですが、地図をみて、自分の通過するポイントや所要時間を確認しましょう。また、ヤマレコやyamapなどで、他の登山者の記録をみて、最近のルート状況に危険や変化がないか確認します。
2 紙の地図とアプリの地図をダウンロードしておく
最近は、簡単なルートだと携帯の地図データのみを持って、紙の地図を持たずに行動する人も多いかと思います。
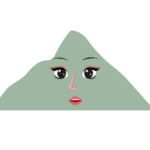
私もハイキング程度だとやってしまいますし、わたしの周りにも多いです(^^;)
でも、携帯のデータのみだと、携帯を無くしたり電池がなくなったら、道が分からなくなり、遭難につながります。必ずスマホの地図データと紙地図&コンパスを両方持ちましょう。紙の地図は、雨などで濡れても良いようマップケースに入れるのがおすすめです。
3 地図読みを習得する
紙地図を持っていても、地図とコンパスを使った読み方を知らなければ意味がありません。自分で理解できなければ、地図読み講習を受けることをおすすめします。
4 定期的にGPSで現在地を確認する
GPSアプリは、登山用のものを使うのがおすすめです。以下も参考にしてください。
ヤマレコやyamapで行先の地図データをダウンロードして、登山中にダウンロードした地図上で現在地を確認します。特に登山道の分岐では確認しましょう。スマホのGPSには数m~30mほど誤差があるとのことです。そのため、分岐を少し進んだところでも、自分が進みたい方に正しく向かっているかを確認したいところ。
その際には、紙地図とも現在地を照らし合わせておくと、急にスマホの地図情報が見られなくなり、紙地図を見なきゃいけなくなった時に、現在地を特定するのがスムーズになります。
5 道迷いしたら、沢を下らない
私の体験談のガイドさんの教えにもあるように、現在地が分からなくなったら、下らずに上に向かうことです。それそれの尾根は、上に行けば行くほど一つのピークや稜線に集結するので、いつかは登山道に出るはずです。
逆に、下って沢に入ってしまうと、がけや滝が多く、もろい場所も多く危険です。
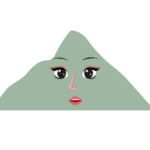
沢登りも、滝を登るのは簡単だとしても、下るとなるとロープで懸垂下降が必要なことが多いですからね~。
一般登山で道迷いした人が、ロープなど持っているわけもなく、そのような危険な箇所を無理して降りようとしてしまい、滑落することがあります。
転滑落の対策
1 滑らないソールの靴を履く
登山靴のソールは、運動靴と違い滑りにくい素材のゴムを使っていたり、ソールの溝が深いため、しっかり地面にくいこむことで滑りにくくなっています。
高尾山や丹沢の大山など、簡単なイメージの山でも、ルートによってはやはり登山靴を推奨します。
2 急いで歩かない
最近トレイルランが流行っているからか(ではないか笑)一般登山者でも下山時にガーっと駆け下りるようにして歩いていく(走っていく)人を見かけます。
そして、そういう人がたまに足を踏み外したり、不安定な石の上に足を置いてしまったりして転倒しているのも見かけます。
下山ダッシュは、自分が危ないだけでなく、近くの登山者も転倒時に巻き込んでしまう場合もあるので気を付けましょう。(私もたまにトレランするので、あくまでも気を付けましょうとだけ言います・・・(笑))
ただ駆け下りるのが好きという人もいますが、公共交通機関の時間に間に合わないなどの理由で、急いで下山して転んでしまうこともあります。そんな方は、急いで下山しなくてもいいよう、時間に余裕を持った計画を立てるべきです。
3 岩場や急登は手も使い登り降りする
岩場の登りは自然と岩を手でつかんで登ると思います。岩のない急登で、尾根が細かったり、フィックスロープなども設置されていないところでは、木の根などをつかんで、身体を安定させてよじ登るのも有効です。ただし、全体重をかけないこと。
下りは、前向きで降りるだけでなく、後ろ向きになり、地面い生えているつかめるものをつかんで降りる「クライムダウン」という方法も安全に降りる方法の一つです。ただし、下る方向前が見えにくいので、慣れていない人ははじめは怖いかも。
本格的な岩場のある登山を今後していきたいというのであれば、ボルダリングなどで、登る練習と合わせてクライムダウンの練習をすることをお勧めします。
4 危険個所は脆さを確認してから通過する。
上記の、「つかめるものはつかんで体を安定させる」ことは大事ですが、掴んだものが必ずしも堅牢とは限りません。体重をかける前に、掴んでいる岩や木を少しゆすったりして、本当に崩れないかどうか確認してから力をかけましょう。
また、その際あまりに力強くゆすったりすると、落石や落下物を発生させる可能性があるので、優しくゆすって確認し、確認した岩や木を掴むときも、全体重をかけずになるべく添える程度にします。
滑りそうな地面や木の上を通過するときも同様です。足を置くことを避けるか、どうしても足を置く必要があるなら、そっと真上から置いてなるべく横への力を加えないようにします。
病気の対策
なかなか難しいですね・・・。
統計的には、山で発生する急病は、心疾患が多いらしいです。
ですが、もともと持病を把握していた方より、疾患を把握しておらず登山をしていて、山で病気が発してしまった、というケースが多いようですので、この対策としては、「事前に心疾患の持病がないかを検査しておく」ということくらいでしょうか。
何の自覚症状もないのに、心臓の検査をしに行くなんて普通は腰が重くてしないのでしょうが、(当然自分もそうです)「登山者外来」というものが長野県の病院にはあるようなので、こういった検査を受けてみて、登山における内因性のリスクについて把握しておくのは、結構大切かもしれないです。
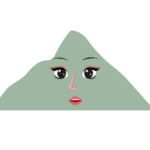
北アルプスの帰りにでも、受けてみたいなぁ。料金高いけど・・・
あとは、自分の命を守るための対策とは言えないかもしれないですが、仲間が急病で倒れたときに、AEDが有効な場合があるので、AEDの使い方について学ぶこと、通過する山小屋にAEDがあるかを確認しておくこと、も大切ですね。
疲労の対策
疲労対策で私が一番必要だと思うのは、言うまでもなく「体力をつけること」です。登山は長時間行動で持久力が必要ですし、筋力も必要です。私は、10kmのジョギングとサーキットトレーニングで心拍数を挙げるトレーニングを各2回/週やっています(好きだからやっていますが・・・)。
また、登山中の栄養補給と登山前の十分な睡眠も重要な要素です。私は体力には自信がありますが、夜の車移動で3~4時間くらいしか寝られずに出発するときは、やはり体力がつらいです。
また、水分補給を怠ったり、おなかが空いているのに無理して補給せずに歩き続けていると、それも疲労感に繋がります。
体力は一朝一夕では得られませんが、十分な睡眠と栄養補給はすぐに実践できるので、ぜひやってください。
まとめ
山での遭難手前の体験談と対策について紹介しました。
山でよくある事故を知り、その対策を徹底的に練ることで、遭難発生のリスクはだいぶ減ると思います。
ですが、上記で紹介したこと以外にも、行先や季節により新たなリスクが生まれる場合もあります。例えば、真夏の炎天下の山行は、熱中症のリスクがありますし、夏から秋の季節の変わり目は、思ったより気温が低下し低体温症のリスクが上がったりします。雨の翌日は登山道が滑りやすくなっており、転滑落のリスクが上がるかもしれません。
始めのうちは、何が危険要因なのか気づきにくいと思いますので、やはり経験者豊富な人と行くのがおすすめです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。





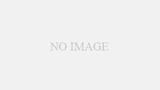
コメント