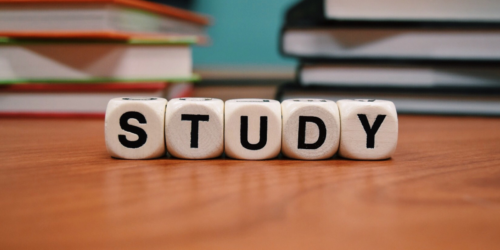
6484字
登山にはまっていくと、「改めて基礎から学びたい」「知識や技術を極めたい」「山を仕事にしたい」などの理由で、資格の取得を考える人も多いのではないでしょうか?
ここでは、2025年に受験可能な登山に関する資格について、試験日程や内容、難易度などを紹介します。
登山に関するおすすめの資格5選
登山が好きな方にお勧めの資格を5つ紹介します。
日本山岳ガイド協会認定ガイド
日本山岳ガイド協会(JFMGA)認定ガイドは、登山や自然ガイドのプロフェッショナルとして、安全で楽しい登山体験を提供するための資格です。JFMGAは、登山ガイド、山岳ガイド、自然ガイドなど、さまざまなガイド資格を提供しています。
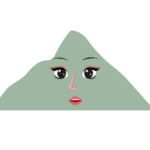
勘違いしている人が多いけど、日本山岳ガイド協会の資格がなければ全国の山をガイドできないわけではないです。ガイド資格を持っていない人が一般人をガイドしても、違法にはなりません。(持ってないと信頼度は低いですが・・・)
日本山岳ガイド協会の主なガイド資格
- 自然ガイド:自然環境や歴史、民俗などを解説するガイド資格。ステージIとIIがあります。
- 登山ガイド:無雪期の一般登山道でのガイド行為を行う資格。ステージIからIIIまでの段階があります。ステージⅡ
- 山岳ガイド:通年での山岳地帯でのガイド行為を行う資格。ステージIとIIがあります。
※他にも、国際山岳ガイドや、フリークライミングインストラクター、スキーインストラクターなどの資格がありますが、ここでは特に「山歩きや、山に登ることに関する資格」のみ紹介します。
1 自然ガイドⅠ、Ⅱ
国内において四季を通じて、人間社会と隣接する里地・里山・山地・高原において自然、歴史、民俗等を解説する自然ガイド行為を行う事ができる。
自然ガイドⅠとⅡの違いは「積雪期の里山・里地を案内できる」か否か。ただしⅡでも森林限界を超える場所は案内できません。
2 登山ガイドⅠ、Ⅱ、Ⅲ
・登山ガイドⅠは、「国内の無雪期においての山地・山岳地帯での整備された登山道で、登山ガイド行為を行う事ができる」資格になります(無雪期のみガイド可能)。
・登山ガイドⅡは、「国内の四季を通じて山地・山岳地帯での整備された登山道で、登山ガイド行為を行う事ができる」資格です(積雪期も含め1年中ガイド可能)。ただし、積雪期は森林限界を超えない2~3時間程度のルート限定です。
また、上記の登山ガイドⅠ、Ⅱはあくまでも「整備された」ルートのみガイドが可能で、地図上の破線ルートや難路と言われるルートのガイドはできません。
・登山ガイドⅢは、「国内で四季を通じて登山道が示されているコースの登山ガイド行為を行うことが出来る。」資格です。ただし、積雪期においては、通年営業を行う施設(山小屋、レストハウスなど)から日帰り可能な容易な雪山登山限定でガイド可能です。
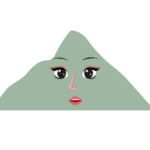
これより高い山や岩稜帯、雪稜登山、沢登りなどのガイドは、上位資格の「山岳ガイド」資格が必要です。
3 山岳ガイドⅠ、Ⅱ
・山岳ガイドⅠは、「通年の国内山岳と縦走路のある岩稜コースや沢登りのガイドが可能。国内にて一年を通して登山ルートのガイド行為を行うことができる」資格です。ただし、岩壁登攀(アルパインルートということだろうか)、雪稜バリエーション、積雪期の岩稜バリエーション、フリークライミング講習は不可。
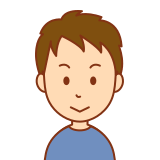
ロープを出さないバリエーションルートはokということなのかな・・・?
・山岳ガイドⅡは、国内最強ガイド資格です。日本国内で季節を問わず全ての山岳ガイドおよびインストラクター行為を行うことができます。
2025年の日本山岳ガイド協会の受験資格や資格試験日程は?
2025年の日本山岳ガイド協会の受験資格や試験日は以下のとおりです。満18歳以上であることが前提です。
簡単に説明すると、筆記試験(1次試験)に合格した方が実技試験を受けられます。
ガイドの種類により、実技検定試験の科目数は様々です。すべての検定に合格し、合格者の義務講習を受けて認定となります。
2025年の試験日は未定ですが、2024年はこちらの日程で開催されたようでした。
【自然ガイド】
| ステージ | 受験資格 | 試験内容 | 費用 | 2025試験日程 |
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ |
・通算100日以上の自然体験活動経験 ・救急法講習受講 ・その他協会が定める条件有 | 【筆記試験(1次試験)】 ・自然解説の基礎知識と技術 ・安全管理とリスクマネジメント ・ガイド業知識 ・小論文 【実技試験(2次試験)】 ・ルートガイディング、安全管理、自然解説技術など | ・検定料:27,500円 ・実技講習費: 38,500円 | 複数回実施 例:R7年5月15日(水) – 19日(日)上高地など |
| ステージⅡ | ・ステージⅠの資格 ・通算100日以上(うち10日は積雪期)の自然体験活動経験 ・より高度な自然解説能力 ・その他協会が定める条件有 | 【筆記試験(1次試験)】 ・自然ガイドステージⅠ有資格者はなし 【実技試験(2次試験)】 ・積雪期のルートガイディング、安全管理、自然解説技術など | ・検定料: なし ・ 実技講習費: 44,000円 | 複数回実施 |
【登山ガイド】
| ステージ | 受験資格 | 試験内容 | 費用 | 2025試験日 |
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | ・通算120日以上の登山経験 ・うち積雪期の雪山登山経験が10日間以上 ・救急法講習を受講している ・その他、協会が定める条件を満たしている | 【筆記(1次)試験】 【実技(2次)試験】 ・無雪期における基本的な登山技術 ・地図読みやコンパスワーク ・ロープワークの基礎 自然解説の基礎 など3科目 | 検定料: 30,000円程度 実技検定・講習費: 計121,000円 | 未定 実技試験は、科目ごとに年2~5回実施日を選べる |
| ステージⅡ | ・120日以上の登山経験 ・うち12月下旬から2月下旬の寒く降雪の多い時期の登山経験が20日間以上 ・協会が定める条件を満たしている | 【筆記(1次)試験】 【実技(2次)試験】 ・無雪期における基本的な登山技術 ・地図読みやコンパスワーク ・ロープワークの基礎 自然解説の基礎 など5科目 | 検定料: 30,000円程度 実技検定・講習費: 計242,000円 | 未定 実技試験は、科目ごとに年2~5回実施日を選べる |
| ステージⅢ | ・登山ガイドステージⅡを取得し、資格認定証の有効期限内である ・正会員として入会後2年以上経過し、100日以上のガイド実務経験がある ・ルートファインディングや登攀技術を要する無雪期バリエーションルート5本以上の先頭経験がある ・沢登り1級以上のルートを12本以上遡行し、すべて先頭を務めた経験がある ・森林限界を超える積雪期の雪山登山経験が40日以上あり、そのうち10峰以上はピッケルやアイゼンを使用した登山である ・危急時対応技術講習会またはファーストエイド講習会を修了している | 【書類(1次)審査】 【実技(2次)試験】 ・無雪期における基本的な登山技術 ・地図読みやコンパスワーク ・ロープワークの基礎 自然解説の基礎 など3科目 | 書類審査料: 5,500円 実技検定費: 計187,000円 | 未定 実技試験は、科目ごとに年2~5回実施日を選べる |
登山ガイドⅡまでは、通年山に行っている人なら受験資格は得られやすいですが、登山ガイドⅢになると、ガイド経験が100日必要となります。趣味で取るにしては、なかなか受験条件が厳しい・・・
【山岳ガイド】
| ステージ | 受験資格 | 試験内容 | 費用 | 2025年試験日程 |
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | ・300 日以上(以下を含む) ・積雪期の標高 2000m 以上の経験が 100 日以上 ・積雪期幕営山行 4泊5日間以上を3回以上 ・登攀は無積雪期 3 級+以上を 15 本以上、積雪期は3 級―以上を 10 本以上 ・フリークライミングはトラッドクライミングルートとスポーツクライミングルートの10aレッドポイントが各 15 本以上 | 【書類(1次)審査】 登攀歴・ガイド歴、作文など 【体力・適正試験(1.5次)】 クライミング、荷物を背負っての登山道歩き 【筆記試験(1.5次)】知識、小論文 【実技試験(2次)】 無雪、積雪、残雪期の登山技術 | 書類審査: 5,500円 体力・適正試験:33,000円 筆記試験:22,000円 実技試験6科目計: 451,000円 | 未定 実技試験は、科目ごとに年2~5回実施日を選べる。 |
| ステージⅡ | ・ステージⅠの資格を有すること。 ・ ステージⅠを超える既定の登山経験を有すること。 ・積雪期の標高2500m 以上の経験が 180 日以上 ・積雪期幕営山行4泊5日間以上を5回以上 ・その他協会が定める条件を満たすこと。 | 【書類(1次)審査】 登攀歴・ガイド歴など 【実技試験(2次)】 無雪、積雪、残雪期の登山技術 | 書類審査: 5,500円 実技試験5科目計: 308,000円 | 未定 実技試験は、科目ごとに年2~5回実施日を選べる |
山岳ガイド受験資格は、豊富な山行経験と、登攀スキルが必要となります。
これらのスキルがなければそもそも受験さえもできない・・・人の命を預かるので当然といえば当然ですね。
東京山岳連盟の登山ガイド資格
東京都山岳連盟のガイド資格は4種類あります。
東京都山岳連盟のガイド資格
- トレックガイド(TGB)
- テクニカルトレックガイド(TGT)
- ミットガイド(SG)
- エキスパートガイド(EG)
1 トレックガイド(TGB)と職能範囲
無積雪期には、信州山のグレーディングA~Cに相当するコースの有償ガイドが可能です。
積雪期には、森林限界を越えない範囲のコースの有償ガイドが可能です(例:北八ヶ岳、奥多摩、丹沢)。
また、職能範囲内で有償の講習会も開催できます。さらに、プロガイド養成委員会が主催する企画に参加する場合、すべてのコースでの有償ガイドおよび有償講習会の実施が可能です。
2 テクニカルトレックガイド(TGT)と職能範囲
無積雪期には、信州山のグレーディングA~Eに相当するコースの有償ガイドが可能です。また、滝以外で転落の危険性が低い日帰りの沢登りコース(例:モミソ沢、マスキ嵐沢など)の有償ガイドも行えます。
積雪期には、営業中の山小屋から日帰り圏内で危険箇所が一部に限られる雪山(例:八ヶ岳硫黄岳、北八ヶ岳天狗岳など)の有償ガイドが可能です。
また、職能範囲内での有償講習会も実施できます。さらに、プロガイド養成委員会が主催する企画に参加する場合、すべてのコースでの有償ガイドおよび有償講習会の実施が可能です。
3 サミットガイド(SG)と職能範囲
無積雪期には、山岳クライミングや渓谷遡行を含むすべてのコースの有償ガイドが可能です。積雪期には、平易な冬期バリエーションルートや残雪期の一般登山コース(例:八ヶ岳赤岳、西穂高岳独標など、阿弥陀岳北稜、大同心稜など)の有償ガイドが行えます。また、職能範囲内で有償の講習会も開催できます。さらに、プロガイド養成委員会が主催する企画に参加する場合、すべてのコースの有償ガイドおよび有償講習会の実施が可能です。
4 エキスパートガイド(EG)と職能範囲
季節を問わず、すべての山岳での有償ガイドが可能です。また、職能範囲内で有償の講習会も開催できます。
登山インストラクター資格(SMPO日本安全登山推進機構)
私も登山インストラクターの資格を持っています。現在はSMPOという団体に移管したそうですが、私が取得した時は日本登山インストラクターズ協会(JMIA)という団体が母体でした。
登山ガイド資格は、同行者を山に安全に案内する知識、技術を習得できるのに対して、登山インストラクター資格は、一般登山者として知識を深めたり、一般登山者である自分が、相手に対して登山技術を指導するといった視点での内容になります。
登山インストラクター資格は3種類あります。
登山インストラクター資格
- 登山リーダー認定
- 登山基礎技術認定
- 登山技術指導者認定(登山インストラクター)
1 登山リーダー認定
- ハイキングやトレッキングを安全に実施するための知識を証明する資格です。
- Web上での動画学習と座学試験、そして実技試験があります。
2 登山基礎技術認定
- 安全に登山をするための基礎的な技術を習得するための資格です。
- 地図読み、ロープワーク、救急法などを習得します。
3 登山技術指導者認定(登山インストラクター)
- 登山技術を指導する専門家としての能力を証明する資格です。
- 1年間の養成講座を受講し、修了検定に合格する必要があります。
- 登山パーティーのリーダーや教育機関の講師など、登山技術を伝える指導的立場にある方を対象としています。
SMPOの最上位資格である登山技術指導者認定(登山インストラクター)は、1年を通じて、オンラインと実地の講習を受け、山行に必要なロープワークやレスキュー、ファーストエイド、雪山、沢登りでの基本的な技術を学び、最後に検定を受けます。年間を通じて同じメンバーで講習を受けるので仲間もたくさんでき、山友達をつくるのにも良いですよ!
山の知識検定(日本山岳検定協会)
正直この検定についてはよく知らないですし、活用方法もわかりませんが(笑)、山の雑学が増えて話のネタになりそうです。
今年の試験日は、2025年6月29日(日)で、東京会場のみとなります。
| コース | 試験内容 | 受験料 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| ブロンズ | ・地図記号、地図の読み方 ・登山装備、ウェア、マナー ・代表的な動植物の知識 ・ 山の地形、地学に関する知識 ・ 天気図記号、天気のことわざ など | 4,400円 | 初心者~中級者向け |
| シルバー | ・ブロンズコースの内容より専門的な知識 ・ 複雑な地形の読図 ・植物の特徴 ・ 全国各地の山の位置関係 など | 5,500円 | 中級者~上級者向け |
| ゴールド | ・シルバーコース合格者のみ受験可能 ・より高度な専門知識 ・実践的な応用力 | 7,700円 | 上級者向け |
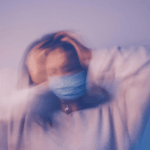
試験で難しい買ったのは、植物の名前を答えるものだったよ。個人的に植物の名前を記憶するのが苦手だったけど、白黒の写真を掲示されるので、より難しかった(^^;)
ウィルダネスファーストエイド(WMA Japan)
ウィルダネスファーストエイド(Wilderness First Aid, WFA)は、自然環境での救急対応スキルを学ぶための講習です。医療施設が遠い場所で発生する怪我や病気に備えることを目的とし、傷病者評価、心肺蘇生法(CPR)、骨折や出血の処置、低体温症や熱中症への対応、搬送方法などが含まれます。アウトドア活動をする個人やプロフェッショナル(ガイド、救助隊員)に特に有益で、緊急時に冷静かつ効果的に行動する力を身に付けることができます。
私も救急法を受講していたので少し知識はありましたが、ウィルダネスの講習内容はアウトドアに特化したものですごくためになりました。事前にオンラインで知識を入れて、実技講習では予習内容を確認した後にシミュレーションをやっていくのでしっかりと段階的にスキルが身に着く感覚がありました。費用は高いけどお勧めです。
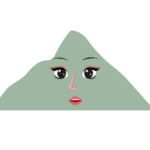
私はアドバンスの方を受講しましたが、登山ガイドさんやアウトドア関連でお仕事されている方の参加が多かったです。ベーシックだと一般登山者の割合がもう少し増えるのかも?
| コース名 | 内容 | 費用(目安) |
|---|---|---|
| WFA(ベーシックレベル) | 傷病者評価システム、一次救命処置(CPR、AEDなど)、骨折や熱中症の対処法、低体温や溺水への対応など | 約30,000~50,000円 |
| WAFA(アドバンスレベル) | 長期的なケア、脊椎マネジメント、体温調節、アレルギー対応、シミュレーション実習など | 約60,000~80,000円 |
| WFR(プロフェッショナルレベル) | 高度な救急法、チームレスキュー、捜索救助、緊急出産対応など | 約100,000~150,000円 |
ウィルダネスファーストエイドで学ぶ主な内容
ウィルダネスファーストエイドでは主に以下の内容を学びます。
1. 傷病者評価
- 現場での安全確認と傷病者の状態評価(意識レベル、呼吸、血流の確認など)。
- 緊急時の優先順位を判断する「トリアージ」。
2. 一次救命処置
- 心肺蘇生法(CPR)と自動体外式除細動器(AED)の使用。
- 出血の止血方法(圧迫止血、包帯の使用など)。
3. 野外特有の応急処置
- 骨折や捻挫の固定方法(スプリントの作成など)。
- 低体温症、熱中症、凍傷、脱水症状への対応。
- 動物の噛み傷や刺し傷、毒性植物の対処法。
4. 搬送技術
- 負傷者を安全に移動させる方法(担架の即席作成、チーム搬送など)。
- 救助が遅れる場合の長期的なケア技術。
5. シナリオベースの訓練
- 実践的なケーススタディや模擬状況での練習を通じ、判断力と技術を磨く。
6. 限られた資源の活用
- 野外で入手可能な材料を用いた即席応急処置。
まとめ
いかがでしたか?
間もなく新年度がはじまり、新しいことにチャレンジしようという方も多いと思います。
趣味の領域ではありますが、何か形に残る目標を設定したら、モチベーションにもつながると思いますので、ぜひ、資格にチャレンジしてみてください。
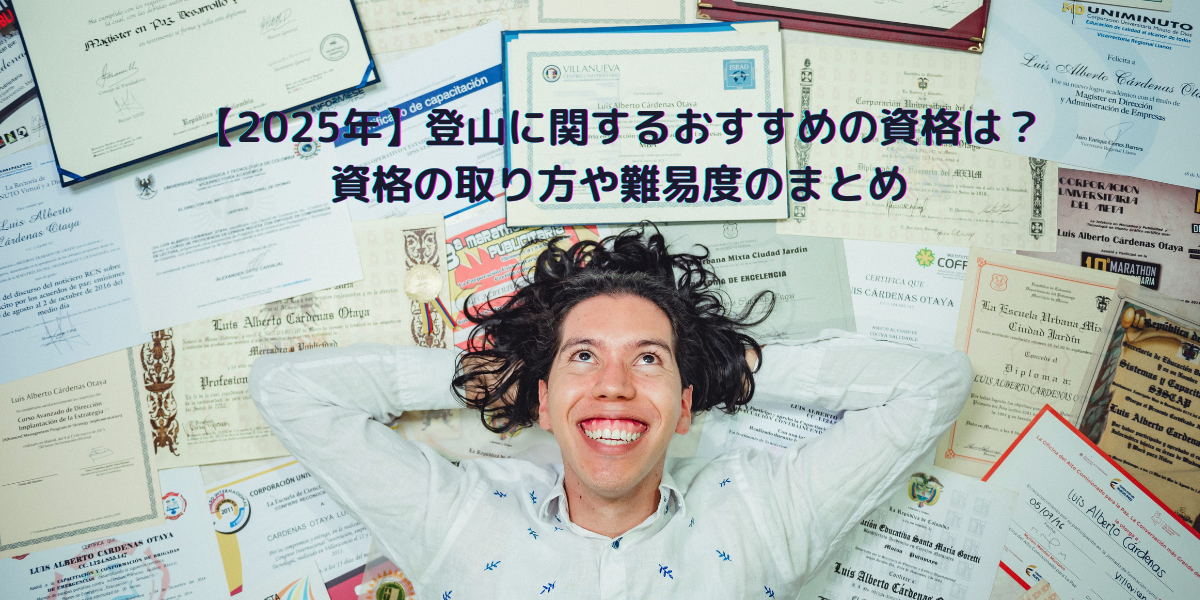

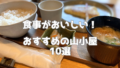
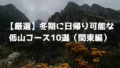
コメント