2025年1月19日(土)に、冬の谷川岳西黒尾根に登ってきました。山行記録やルート状況、難易度を紹介します。
谷川岳のメジャールートは、夏も冬も天神尾根と西黒尾根の2つがあります。天神尾根はロープウェイ利用可能な岩場が少ない初心者向けルート。西黒尾根は日本3大急登の一つである尾根を登る、一般登山道の中では中級ルート。今回は、後者の西黒尾根を登りました。
実際のコースタイム
6:30谷川岳ベースプラザ駐車場~6:45谷川岳山岳資料館~7:00西黒尾根登山口~9:20ラクダの背(ラクダのコブ~9:23ラクダのコル~10:20ザンゲ岩~10:55肩の小屋~11:10山頂(トマノ耳)~11:20谷川岳(オキの耳)~11:50肩の小屋~12:05天狗の留まり場~12:40熊穴沢避難小屋~12:53天神尾根・田尻尾根分岐点~13:44田尻尾根登山口~14:45駐車場
装備(衣類除く)
インナーグローブ、アウターグローブ、ハードシェル上下、ロングスパッツ、バラクラバ、替えグローブ、ザックカバー、12本爪アイゼン、ピッケル(ストレートシャフト)、行動食、水筒(保温性)、緊急用ガスカートリッジ、緊急用ストーブ、小コッヘル、ライター、紙地図(地形図)、コンパス、笛、計画書、ヘッドランプ、予備電池(単3、単4)、ボールペン、ファーストエイドキット、日焼け止め、ティッシュ、保険証、携帯電話、時計、サングラス、ゴーグル、ツェルト、ナイフ、コンパクトデジタルカメラ、ヘルメット、わかん、ストック1本、携帯用バッテリー
山行記録
山の先輩から、谷川岳の天気について、以前こんな話を聞かされた。

谷川岳は、年間に「晴れる日」が10日ほどしかないらしい
本当か?と思う。山の先輩も「そんなことないと思うけど・・・」という。
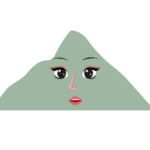
まず「晴れる日」の定義があいまいだよな・・・(笑)
確かに、地形的には日本海と太平洋を分ける分水嶺なので、日本海、太平洋側の両側から流れる空気の影響を受けやすいため、実際に天候が変わりやすいことはあると思う。
そうはいっても、自分自身、ここ5年間で10回以上は行っている谷川岳。そもそも、すんごく天気が悪い予報なら行かないし、かといって、一日中ドピーカンだった日にも当たったことはないので、この言葉が正解かどうか確かめるのは難しいが、5割の確率くらいで良い天気の日に行けていると思う。
いずれにせよ、致命的な悪天候を避けられればなんでも良い。
この日は複数の天気予報(ヤマテン、てんきとくらす、windy、ウェザーニュース)を見ても天気、風速ともに1日中好条件の予報。
・・・これが1年に10日しかない最高の条件の日なのか?
本日の同行者は雪山初心者の友人。あまり過酷な環境だと誘ったことに罪悪感を感じてしまうので(笑)今日は良い条件で登れるなー、と素敵な1日に期待して出発。
この日の行程は、西黒尾根を登り、天神尾根を使い天神平付近まで下山、その後ロープウェーは使わずに、それと並行する田尻尾根を歩いて下山するというルート(ロープウェーが高いんですわ)。
6時に谷川岳ベースプラザ着。1階はこの時期、夜も無料開放でありがたい。(平日は火、水曜日は閉鎖するようなのでご注意を。)
前日も天気が良く、この日も好天と駐車車両多数のため先行者がいるだろうと思い、初めからトレースはあるだろうと期待はしていた。が、下山の田尻尾根の利用者が少なそうなので、わかんは持っていくことにする。
6時半に駐車場を出発し、まずは標高900mの鉄塔がある稜線まで上がる。
稜線までは様々なルート取りでトレースがついているが、
ここはみんな自由に降りてるからかいろんなとこにトレースがある。わかんの下りトレースを辿ってしまったので、ツボ足では沈みまくってちょい体力を消耗したが、先週の聖に比べたら、全く大したことない( ̄ー ̄)

標高900mまで上がり、稜線に出た。

あとはひたすら登り。
アルパインルートの東尾根が、すぐ近くに見える。

谷川岳の馬蹄形を構成する山々がきれいに見える。あそこも冬に歩いてみたい。

1450mくらいになると森林限界になり、周囲の視界が開ける。このあたりが夏道だと鎖が出ている箇所らしい。

森林限界以降、周囲の景色にうっとりしながら歩いていたが、途中に雪庇ギリギリを歩くトレースがあった。そのトレースは途中で雪庇が崩れ、トレースが途切れていおりちょっと我に返る。落ちたのか?恐ろしや・・・
ラクダのコルから先、1500mから1600mくらいまでは、少し傾斜がキツくなる。この日はステップが切ってあったので楽に登れた。先行者に感謝。

傾斜のキツい箇所を振り返るとこんな感じ。

西黒に来る前に色々な記録を見ていて、結構切り立ったリッジが続くのかと思っていたが、実際にはそこまでシビアなリッジはなかった。上の写真を見ても確かに細いリッジの連続のように見えるけど・・
登りに登り、天神尾根との合流地点が近づいてきて、天神尾根側からの登山者が見えてくる。

間もなく、肩の小屋に到着し、小屋を通過して山頂へ。
11:10 谷川の本物の山頂である、手前のトマの耳へ。
谷川岳山頂は、トマの耳とオキの耳の双耳峰である。いつも、どちらがどちらだか分からなくなるため、「オキの耳は天神尾根から来たら”奥”にあるから”オキ“」「トマは”手前”を訛らせて”トマ”」と適当に自分で覚え方を考えたのだが、調べたら、由来はあながち間違っていなかった。

トマが本物の山頂なので、さらに10分歩いた先にあるオキの耳は行かなくていいかな~と思っていたら、相方が「行きたい」というので、行くことにする。
オキの耳から見るトマの耳がカッコよかったので1枚撮影した。

下山は天神尾根を利用する。下山中も、天神尾根からの登山者が次々と登ってくる。
この時間は太陽が照り付けており、しかもほぼ無風なのですごく暑い。半袖になりたいくらい。
やはり今日は冬の谷川岳にしては、上出来な天気ではないか??
ロープウェイを使わずに下山したいので、天神平スキー場の手前まで下り、途中の分岐から田尻尾根を利用。

田尻尾根はトレースが薄くて踏み固められたものはなく、アイゼン歩行だと身体が沈んで体力を消耗したので、途中からわかんを使用した。
わかんで調子が上がり、14:30には田尻尾根の基部に着いた。残りは綺麗に均された道を歩いたが、途中でスキーヤーが何人か滑走して抜かされたため、滑走路だと気づく。
谷川岳では、まだ雪山を初めて間もない頃、天神平スキー場における登山者の利用ルールを知らないまま先輩の後ろをくっついてスキー場のど真ん中を横切ろうと歩き、その先輩を筆頭にスキー場スタッフやスキー客にきつく注意された記憶があった。
今回も、同じスキー場なので、また叱られるんじゃないかと内心ビビッていたが、横切ったパトロールの兄ちゃんには、登山者は端を歩いてスキー客と接触しないようにとの注意は受けたものの、優しかったのでほっとした。
14:45、駐車場に戻り下山した。
感想と難易度
当日の西黒尾根には前日のトレ―スがあり、ラッセルが必要なくてルートのコンディションが非常に良かったのでおおむね予定通りに進むことができました。
その上、天候についても風がなくて視界クリアだったので、難しいルートファインディングもありませんでした(当然雪庇の通過はトレースを鵜呑みにせずに、安全確認して歩きました。)。
そのため、この日は難易度としては低かったです。
ただし、先行者がいない場合、天候の条件が良かったとしても難易度はもっと上がります。
理由は主に3つあります。
1つ目は、高度差1000m以上をラッセルする必要があるためです。
谷川岳の雪は、水分量が多くて重みがあり、ラッセルはかなり堪えます・・・
去年は、1月後半に谷川岳周辺の山に行きましたが、1時間で標高100mほどしか上がることができませんでした。
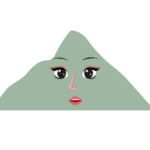
この場合、標高1000mを上がるのに、単純計算すると10時間かかります(笑)。日が短い冬だと、夜明け前から歩けば日没までに下山できないこともないですが・・・
また、2024年の年末に西黒尾根に日帰りで登った知人は、登山口から10人でラッセルしたものの、時間切れで敗退しています。
初心者、初心者でないにかかわらず、トレースなしの西黒尾根は日帰りで行くとタイムアウトになる可能性が高いです。
2つ目は、森林限界以上での雪庇通過とリッジ歩きがあるためです。
雪庇のどの部分を歩いたら危ないか、しっかりと確認しながら歩く必要があります。
西黒尾根は、痩せたリッジが長く続くわけではないですが、夏道だと岩場や鎖場になっているような箇所は、雪の付き方が不安定だったりします。そういう箇所では雪をしっかり踏み固めたり、あらかじめ不安定に積もった雪を落としながら慎重に歩く必要があります。
3つ目は、森林限界より上の傾斜がきつい(人によっては「雪壁」のようにも見える)急登が100mほどあるためです。
ここを怖がらずに登れるかどうか、メンタル的な問題と、急登をしっかり登れるアイゼン&ピッケルワークのスキルが必要です。
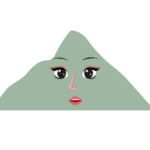
私も高いところが苦手なので、振り返ると結構怖いです・・・。
まとめ
谷川岳西黒尾根は、積雪のある急登、リッジ&雪庇歩きがあり、変化に富んだ登りごたえのあるルートだと思いました。数少ない日帰りで行ける冬山ルートでもあり、時間的に泊まり登山が厳しい人にも向いています。また、森林限界が低いため、登りだしてから早い段階で360℃の展望が楽しめます。
ただし、天神尾根や、他の初心者ルートをいくつか登ってから経験することをおすすめします。
上記の通り、歩き慣れていないと怖いと感じる箇所が多々あるため、上級ルートへのステップアップとしては非常におすすめです。
ぜひ、雪山にある程度慣れた方は、挑戦してみてください。

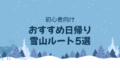

コメント