
冬期(12~4月)に日帰り可能な積雪の少ない低山コース10選
夏山シーズンも終わり、急に涼しくなってきましたね。紅葉の時期も山は綺麗ですが、あっという間にその時期も終わり、冬が始まります。
「冬の澄んだ空気の中で山に登りたい!」「でも、本格的な雪山装備はまだちょっと…」
そう思っている登山愛好家の皆さん、冬の低山は夏とは比べ物にならないほど魅力がいっぱいです。葉が落ちて遠くまで見渡せる絶景、凛とした空気、そして雪化粧をした高山の姿は格別です。
冬の低山は積雪が少なくても、凍結路(アイスバーン)の危険が潜んでいます。しかし、安心してください!「軽アイゼン(滑り止め)」という最低限の冬山装備さえあれば、安全に冬のハイキングを楽しむことができます。
今回は、数ある低山の中から、積雪が少なく、日帰りアプローチしやすい関東周辺の低山10コースを厳選してご紹介します。凍結対策を万全にして、この冬、最高の山歩きを始めましょう!
※以下の山は積雪が少ない地域を選定していますが、冬期(12月~4月)は必ず凍結対策として軽アイゼン(4本爪以上)やチェーンスパイクを携行し、日陰や急斜面の凍結箇所では必ず装着してください。 軽装での転倒・滑落事故が最も多いのがこの時期の低山です。安全第一でお楽しみください。
⛰️ 【低山ガイド厳選】冬期(12月〜4月)に日帰り可能な積雪の少ない低山コース10選
| 山の名前 | 地域・特徴 | 体力度(冬期) | 所要時間・日数(目安) | 営業小屋の情報(冬期) |
| 高尾山 (たかおさん) | 東京。アクセス抜群。登山道・整備度が高く初心者向き。 | ★★☆☆☆ | 日帰り(3〜5時間) | ケーブルカー、茶屋などは通年営業。 |
| 鋸山 (のこぎりやま) | 千葉。海沿いで積雪が極めて少ない。地獄のぞきが有名。 | ★★★☆☆ | 日帰り(4〜5時間) | ケーブルカー利用可。山頂周辺に通年営業の売店あり。 |
| 大山 (おおやま) | 神奈川。丹沢の東端。石段が多く、眺望も良い。※冬季はしっかり積雪することもあり。 | ★★★☆☆ | 日帰り(6〜7時間) | 麓の阿夫利神社付近の茶屋は通年営業。山頂付近は冬季休業。 |
| 宝登山 (ほとさん) | 埼玉・秩父。ロウバイ園が有名。ロープウェイ利用も可。 | ★★☆☆☆ | 日帰り(3〜4時間) | ロープウェイ利用可。山頂に休憩所・売店が通年営業。 |
| 御岳山 (みたけさん) | 東京。ケーブルカー利用可。武蔵御嶽神社があり、宿坊も利用できる。 | ★★☆☆☆ | 日帰り(3〜5時間) | ケーブルカー、宿坊(宿泊施設)、売店は通年営業。 |
| 陣馬山 (じんばさん) | 東京・神奈川。高尾山方面との縦走も可能。開放的な山頂が人気。 | ★★★☆☆ | 日帰り(5〜7時間) | 山頂の茶屋は週末など営業あり(要確認)。 |
| 弘法山 (こうぼうやま) | 神奈川。秦野市の低山。展望が良く、手軽に歩けるハイキングコース。 | ★☆☆☆☆ | 日帰り(2〜3時間) | 休憩所・売店はなし。 |
| 筑波山 (つくばさん) | 茨城。ケーブルカー・ロープウェイ利用可。百名山だが低山。 | ★★★☆☆ | 日帰り(4〜6時間) | ケーブルカー、売店などは通年営業。 |
| 鷹取山 (たかとりやま) | 神奈川・横須賀。岩場があり、クライミングの練習にも使われる。眺望良し。 | ★★☆☆☆ | 日帰り(2〜3時間) | 休憩所・売店はなし。 |
| 塔ノ岳 (とうのだけ) | 神奈川・丹沢。大倉尾根は体力トレーニングに最適。標高が高いため、装備を念入りに。※冬季はしっかり積雪があることもあり。 | ★★★★★ | 日帰り(7〜9時間) | 尊仏山荘は基本的に通年営業だが、天候により変動あり(要確認)。 |
※上記の山でも、積雪がある場合は軽アイゼンとチェンスパイクのみの装備では不十分です。最新の状況を確認して、完全に冬山の様相であれば、行先の変更を検討してください。
冬の低山登山での注意点
1. 装備は「凍結対策」と「防寒・防風」を万全に
「低山だから大丈夫」は冬山では通用しません。以下の装備は必須と考えてください。
| カテゴリ | 注意点・推奨装備 | なぜ必要か |
| 凍結対策 | 軽アイゼン(4~6本爪) または チェーンスパイクを必ず携行。 | 日陰、橋の上、水が染み出す場所は確実に凍結します。軽アイゼンがないと滑落・転倒の危険が極めて高いです。 |
| 防寒小物 | 耳まで隠れる帽子、ネックゲイター(首・口元を覆う)、防水防寒グローブ(予備も)。 | 体の熱は首、頭、手足の末端から逃げます。これらを覆うことで体感温度が格段に上がり、低体温症を防ぎます。 |
| ウェア | ベースレイヤー(吸湿速乾性)、ミドルレイヤー(フリース等)、アウター(防水透湿性)のレインウェアやソフトシェル)の3層構造。 休憩時の保温着も必須。 | 汗冷えが大敵です。綿素材は避け、汗を素早く逃がし、風を防ぐ工夫が必要です。休憩時用にコンパクトなダウンジャケットも携行。ヒートテックは汗をかいたら冷えるので厳禁! |
| その他 | 保温ボトル(温かい飲み物)、ヘッドライト(予備電池込み)。 | 体温維持に温かい飲み物は効果的です。ヘッドライトは、日没の早さに備えた必携装備です。 |
2 日の入りが早い
冬は日照時間が短く、低山でも樹林帯に入ると平地より早く暗くなります。
登る山の日没時刻を調べて、1時間半前には下山するよう、余裕を持った計画を立ててください。
私はこれを使わせていただいてます。⇒ 登山者のための日の出日の入り時刻
| 注意点 | 詳細 | 対策 |
| 日没の早さ | 冬至前後(12月~1月)は、平地でも16時半頃には日が傾き始め、山中は16時を過ぎると急速に暗くなります。 | 日の入り時刻を必ずチェックし、遅くとも日没の1時間半前には下山を完了する計画を立てましょう。 |
| 行動時間 | 積雪や凍結で歩行速度が落ちるため、夏山のコースタイムの1.2~1.5倍を目安に見積もります。 | 朝早くスタートし、遅くとも午後1時~2時をリミットとして、その時間までに山頂に着かなくても潔く引き返す「下山開始時間」を設定します。 |
| 樹林帯の暗さ | 日が当たらない北斜面や深い樹林帯は、昼過ぎでも急に薄暗く感じることがあります。 | 計画通りでもヘッドライトは必ず手の届く場所に入れておきましょう。 |
3. 凍結は最大の事故要因!凍結しやすい場所を知る
低山の冬山事故のほとんどは、凍結箇所での転倒・滑落が原因です。積雪がなくても、凍結対策は必須です。
| 凍結しやすい場所 | 特徴と対策 |
| 日陰の急斜面 | 一日中日が当たらないため、一度凍ると溶けにくいです。軽アイゼンの装着を躊躇せず行いましょう。 |
| 沢沿いや橋 | 水分が多いため、夜間や早朝に急速に凍りつき、鏡のようなアイスバーンになることがよくあります。 |
| 階段・木道 | 木材や石材は熱を伝えにくいため、凍結しやすく、滑りやすいです。特に下りでは足元全体で踏まず、慎重に。 |
| 泥濘(ぬかるみ) | 昼間に溶けた泥や水たまりが、夕方や夜間にカチカチに凍ります。朝の登山では特に要注意です。 |
準備を万全にして、冬のきれいな景色を!
ご紹介した10のコースは、冬の澄んだ空気と壮大な眺望を楽しむのに最適です。しかし、何度も繰り返しますが、冬の低山で最も大切なのは「安全の徹底」です。
軽アイゼンやチェーンスパイクといった滑り止め装備は、凍結路という冬山最大の危険からあなたを守ってくれる大事なアイテム。そして、日没の早さを意識した余裕のある行動計画は、無事に下山するための鉄則です。
都会から近くても、山は決して油断できません。万全の準備と、引き返す勇気をもって、冬山ならではの感動的な景色を味わってください。
冬だからと行って山に行かないのはもったいない!ぜひ低山ハイクに出かけてみてください!
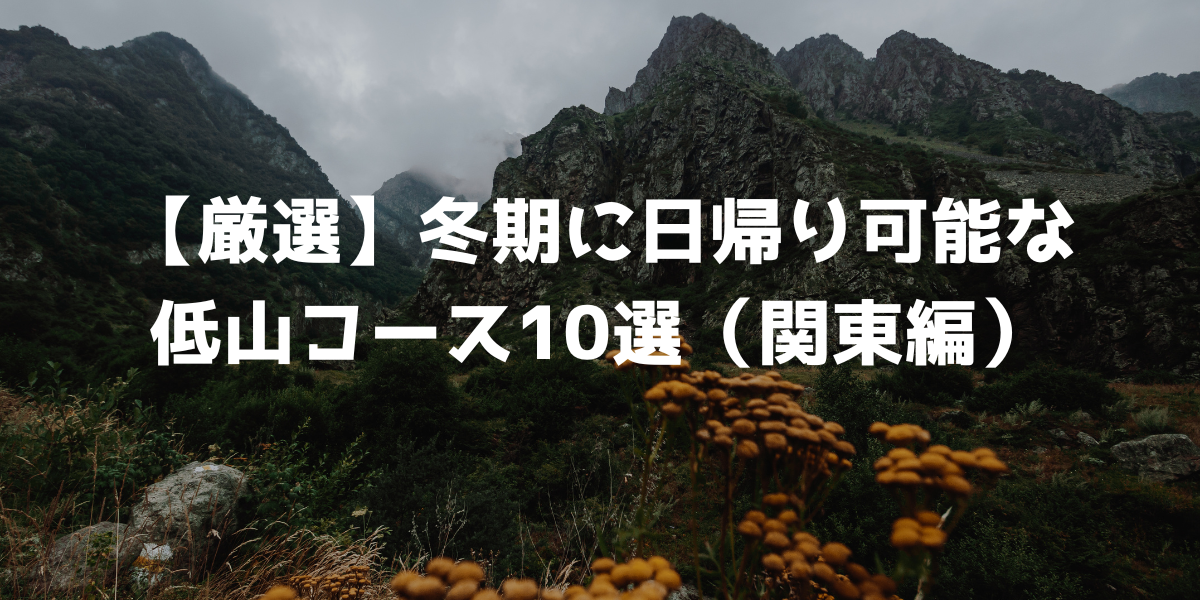





コメント